認知症外来を担当していると、患者さんやご家族から「以前、ほかの病院で“年相応”と言われたんです」という言葉をよく聞きます。一見、やさしく聞こえるこの“年相応”という言葉。しかし、認知症の診療現場では、この一言が「発見の遅れ」や「治療の機会を逃す原因」になることが少なくありません。
私自身、これまでの診療の中で、「以前は年相応と言われたのに、実際は認知症が進行していた」
というケースを何度も経験してきました。もしもう少し早く対応できていれば――。そう思うことも少なくありません。
目次
1.「年相応」とは何を意味するのか?
そもそも、“年相応”とはどういう意味でしょうか。多くの場合、「年齢に見合った状態」というあいまいなニュアンスで使われています。しかし、医学的に見ると、これはとても不正確な言葉です。認知症の診療では、主に次の2つの観点で“年相応”という表現が使われがちです。
- 脳の萎縮(脳の形の変化)が年齢相応かどうか
- 認知機能の低下が加齢による自然な範囲かどうか
ところが、これらはいずれも専門的な知識とデータに基づいた慎重な判断が必要です。
経験則や印象だけで「年相応ですね」と言ってしまうのは、とても危ういことなのです。
2.脳の萎縮と「年相応」
たとえば、頭部CTで脳の萎縮が見られる場合。特に、側頭葉の内側(記憶に関わる部分)や前頭葉などに強い萎縮があるときは、アルツハイマー型認知症などの病気が疑われます。
ところが、脳画像の読影に慣れていない医師の場合、「これは加齢による変化、年相応の萎縮ですね」
と判断してしまうことがあるのです。実際、以前ほかの医療機関で「年相応」と言われた方のCTを当院で見直してみると、すでに認知症の中期に入っていたというケースもありました。このような誤解は、治療のタイミングを逃す大きな原因となります。
3.認知機能スコアと「年相応」
また、MMSE(簡易知能検査)などの認知機能検査でも同じようなことが起こります。この検査は30点満点で、一般的には24点以下が「認知症の疑い」とされます。
ところが、中には20点前後でも「高齢だからこんなもの」と言われてしまうことがあります。実際にはこの点数はすでに中等度の認知症にあたり、「年相応」ではありません。この段階で適切な治療を始めることができれば、生活の質を大きく保つことができます。しかし「年相応だから大丈夫」と見過ごされてしまうと、進行が早まり、介護の負担も急激に増えてしまうのです。
4.「年相応」と言われたときに気をつけたいこと
もし医療機関で「年相応ですね」と言われたら、次の3点を確認してみてください。
-
どの部分が“年相応”なのかを具体的に聞くこと
──画像所見なのか、検査の点数なのか、医師の印象なのか。
何を根拠にそう言われたのかを確認しましょう。 -
必要であれば専門医の意見を聞くこと
──「年相応」と言われても、納得がいかないときは、認知症専門医に相談してみてください。 -
“年相応”=“正常”ではないと理解すること
──高齢者に多く見られることと、それが「病気ではない」ことは別の話です。
5.専門医からのメッセージ
これからの日本では、ますます高齢化が進みます。だからこそ、「年相応だから大丈夫」という言葉が、
認知症の早期発見を遅らせてしまうことのないようにしたいのです。医師が大切にすべきなのは、「病名を伝えること」だけではありません。患者さんとご家族が、現状を正しく理解し、将来に備えられるように支えることです。
そのためにも、曖昧な「年相応」という言葉ではなく、
根拠に基づいた、わかりやすい説明を心がけたいと思います。
6.おわりに
「年相応」という言葉は、やさしく聞こえます。しかしその言葉の裏に、「大切なサインを見逃す危険」が潜んでいることを忘れてはいけません。患者さん一人ひとりの人生には、それぞれの時間の流れがあります。その人らしい生活を少しでも長く続けられるように──。医療者として、そして一人の人間として、私は「年相応」という言葉に安易に逃げず、丁寧に向き合っていきたいと思います。
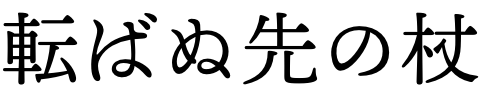


 認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。
認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。