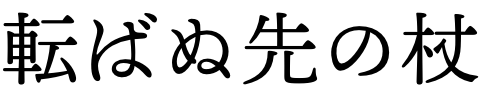先日、DVDで“終の信託”を観ました。
主人公である、折井綾乃(草刈民代)は、患者さんからの評判も良い呼吸器内科のエリート医師です。彼女は、死期が迫っていることを自覚した患者さんから、“信頼できるのは先生だけだ。最期のときは早く楽にしてほしい”と懇願されました。彼女は、約束通り医療を中止しますが、3年後、その決断が刑事事件に発展するという実話を映画化したものです。原作は、現役弁護士・朔立木の同名小説、医師でない視点がとても新鮮でした。
検察官の塚原(大沢たかお)に医師として反発したり、納得しているうちにあっという間に観終わりました。いくつか気づいた点を記載します。
① 終末期医療としては癌の末期や認知症・脳血管障害が一般的です。今回の、患者さんが60歳代で重篤な喘息患者さんというケースは頻度しては少ないものです。このケースだけで終末期医療を語るには無理があります。
② 人工呼吸機につながれていない(=脳死でない)が挿管されている患者さんから管を抜いて苦しんでいる状態での、セルシン20㎎の静脈注射は無理があります。さらに、ドルミカム30㎎を2回など考えれられません。これらの医療行為を医師一人で行うことに無理があります。
③ 検事とは、ストーリをつくって取り調べを進めるもののようです。そのため、自分のストーリー以外のことは聞こうともしません。医師である主人公に対して、『あんたの講義を聴いているわけでない』という発言には、少しカチンときました。
その上、『細かいことは後から聞くから』といって、調書にサインさせようとします。ここで、安易にサインをしてはいけないのですが・・・。
④ 最終的には、懲役2年執行猶予4年の判決となります。良く医師は、『患者さんが自分を信頼してくれる』といいます。しかし、患者さんからすれば、『あんたしかいない』状況であることを忘れてはいけません。いくら信頼してくれると言っても、やはり他の医師と相談する必要はあります。現実にも、同僚と相談することもなく独断で治療を進める医師がいます。今回のケースなどは、個人的にはやはり“独断”であると感じ、判決もやむを得ないと感じました。
⑤ 私自身も時々、初対面の方から“お医者さんですか?”と聞かれることがあります。知らず知らずに、言葉が“医者っぽい説明口調”になっているようです。弁護士さんも、何となく弁護士口調です、映画を観ていても、私が大好きな草刈民代さんを尋問する検察官の喋り方が、当グループの顧問弁護士とかぶってきます。全く関係ないのですが、顧問弁護士に腹が立っていました。
⑥ しかし、本来医師と弁護士とは、対立するものではありません。両者がそれぞれの立場から協力すれば、多くの方を幸せにすることができます。映画を見ながら、そんなことを考えていました。お勧めの映画です。