戦国時代を描いた小説は数多くあります。剣豪の武勇、智将の策謀、派手な合戦――それらは確かに読者の心を強く惹きつけます。しかし今村翔吾の塞王の楯は、そうした戦国小説の王道を、あえて横から切り崩す作品です。
この物語の主役は、刀でも鉄砲でもありません。
「楯」――すなわち、守るための技術と思想です。
目次
1.舞台は関ヶ原前夜・大津城
物語の舞台は慶長五年(1600年)、天下分け目の関ヶ原合戦を目前に控えた近江・大津城です。
石田三成率いる西軍と徳川家康率いる東軍が全国を巻き込んで激突しようとする中、大津城は京への要衝として極めて重要な拠点でした。
城を守るのは京極高次です。そして、その大津城の防御を支えるのが、石垣構築の集団「穴太衆(あのうしゅう)」です。
2.穴太衆と「塞王」
穴太衆は、実在した石垣職人集団です。彼らは戦場で刀を振るうことはありません。しかし、彼らが積み上げた石垣は、幾万の兵を食い止め、多くの命を守ってきました。
その中でも、圧倒的な技と思想を持つ者に与えられる称号が「塞王(さいおう)」です。
塞王とは、単なる職人の頂点ではありません。
「城とは何のために存在するのか」を知り尽くした者にのみ許される称号です。
城は敵を倒すためのものではありません。
城は、戦をさせないための装置です。
これが塞王の根本思想です。
3.対する存在、「最強の矛」
一方、城を攻める側として描かれるのが、国友衆を中心とした鉄砲の名手たちです。
彼らは「矛」の象徴であり、当時最先端の殺傷技術を誇る存在です。
彼らの哲学は明快です。「撃てば人は死ぬ。だからこそ戦は終わる」という考え方です。
守ることで戦を止めようとする塞王と、攻めることで決着をつけようとする鉄砲衆。この物語は、「最強の矛」と「絶対の楯」という、極めてシンプルでありながら深い構図で進んでいきます。
4.城攻めは「技術のぶつかり合い」です
『塞王の楯』の城攻め描写は、単なる合戦ではなく「技術の対決」と言ってよいでしょう。
どの角度で撃てば石垣は崩れるのか。どの石を、どの順番で積めば崩れないのか。
そこには感情論や精神論はありません。あるのは、積み重ねられた経験と理屈、そして覚悟です。
人を殺さずに済むならそれが最善だと信じる者と、
殺さなければ終わらないと知っている者。
どちらも、それぞれの立場で正しいのです。
だからこそ、この戦いに単純な善悪は存在しません。
5.「守る者」は報われにくい存在です
物語を通じて繰り返し描かれるのは、守る者の宿命です。
城が落ちなければ、守った功績は歴史に残りません。
被害が出なければ、「何も起こらなかった」と扱われます。
これは現代にも通じる感覚ではないでしょうか。
事故を防いだ人より、事故を処理した人のほうが目立ちます。
問題を起こさなかった努力は、しばしば見過ごされます。
塞王の仕事も同じです。
完璧な楯であればあるほど、その存在感は消えていきます。
6.それでも「楯」は残ります
物語の終盤、時代の大きな流れの前に、城も、人も、理想も完全には守り切れない現実が描かれます。
しかし、それですべてが無意味になるわけではありません。
城は落ちても、
石垣が崩れても、
思想まで失われるわけではありません。
人を守ろうとした意思。
戦を避けようとした工夫。
無名であることを引き受けた覚悟。
それらは確かに、次の時代へと受け継がれていきます。
ここに、本作の最大のメッセージがあります。
7.現代に生きる「塞王の楯」
この作品が現代の読者の心を打つ理由は、私たちの社会もまた「矛」が評価されやすい時代だからでしょう。
成果を出す人、
前に出る人、
戦って勝つ人。
その一方で、
守り続ける人、
問題を起こさない人、
誰かの居場所を静かに支える人。
彼らは目立ちません。
しかし、社会が壊れずに続いているのは、間違いなく「楯」の存在があるからです。
8.おわりに
『塞王の楯』は、派手な英雄譚ではありません。
しかし、読み終えたあと、静かに価値観を揺さぶってくる作品です。
攻めることだけが強さではありません。
守り抜くこともまた、王の道です。
歴史に名は残らなくとも、人を生かし、次につなぐ。
その尊さを、これほど真っ直ぐに描いた戦国小説は、そう多くありません。
「強さとは何か」を改めて考えさせてくれる一冊です。

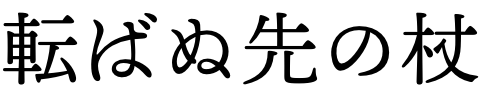


 認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。
認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。