「認知症の患者さんが、がんになるケースは意外と少ないですね」
これは、長年外来を続けている医師であれば、多くの方が一度は感じたことではないでしょうか。私自身、認知症専門外来を続けるなかで、アルツハイマー型認知症の患者さんが、その後がんを発症する例が少ないという印象を強く持ってきました。
実はこの感覚、単なる印象論ではありません。
医学研究の世界では長年、
「がんとアルツハイマー型認知症は、同一人物には併存しにくい」
という現象が注目されてきました。
目次
1.疫学研究が示す「逆相関」
これまでの疫学研究では、
がんの既往がある人は、アルツハイマー型認知症の発症リスクが低い
逆に、
アルツハイマー型認知症は、がんの発症率が低い
という「逆相関(inverse association)」が繰り返し報告されています。
一時は
「がん患者は早く亡くなるから、認知症になる前に亡くなっているだけでは?」
という批判もありました。
しかし、死亡年齢を調整した解析や、長期追跡研究でもこの傾向は消えず、
“統計的な偶然では説明できない現象”
と考えられるようになってきました。
では、なぜこのようなことが起きるのでしょうか。
2.正反対の病気という視点
がんとアルツハイマー型認知症は、分子レベルで見ると驚くほど正反対の病気です。
がんの本質
- 細胞が「死なない」
- 無制限に増殖する
- アポトーシス(細胞死)が抑制される
アルツハイマー型認知症の本質
- 神経細胞が「過剰に死ぬ」
- 増殖できない神経細胞が脱落する
- アポトーシスが亢進する
つまり、
がんは「生きすぎる病気」
アルツハイマー型認知症は「死にすぎる病気」
と捉えることができます。
この“細胞の生と死のバランス”こそが、両者の関係を理解する鍵になります。
3.現在考えられている生物学的機序
生物学的機序としては以下が考えられています。
3-1.p53遺伝子と細胞死の制御
p53は「がん抑制遺伝子」として有名です。
DNAが傷ついた細胞をアポトーシスへ導く、いわば細胞の番人です。
- がんでは:
p53の機能低下 → 異常細胞が生き残る - アルツハイマー型認知症では:
p53活性の亢進 → 神経細胞死が進む
同じ分子が、正反対の方向に働いているのです。
3-2. アミロイドβと腫瘍抑制作用
アルツハイマー型認知症の原因物質として知られるアミロイドβ。
実はこの物質、がん細胞の増殖を抑える作用を持つ可能性が報告されています。
- 神経細胞にとっては「毒」
- がん細胞にとっては「ブレーキ」
同じ物質が、細胞の種類によって全く異なる顔を見せている点は非常に興味深いところです。
3-3.免疫系と炎症反応の違い
がん患者では、慢性的な免疫活性化が見られることがあります。
一方、アルツハイマー型認知症では、脳内免疫(ミクログリア)の暴走が問題になります。
免疫系の「働きすぎ」と「働かなさすぎ」。
このバランスの違いも、両疾患の併存を妨げている可能性があります。
3-4.代謝・エネルギー利用の違い
がん細胞は、いわゆる「ワールブルグ効果」により、
大量のエネルギーを消費して増殖します。
一方、アルツハイマー病の脳では、
- ブドウ糖利用低下
- エネルギー不足
細胞のエネルギー戦略そのものが真逆なのです。
4.外来で感じる「違和感」は、やはり正しかった
認知症専門外来で長く患者さんを診ていると、
- 認知症が進行している方ほど、がんの既往が少ない
- がんサバイバーの方は、認知機能が比較的保たれている
こうした印象を持つことがあります。
もちろん、すべての患者さんに当てはまるわけではありません。
しかし、臨床の実感と研究結果が一致し始めていることは、非常に重要です。
5.これは「良い話」ではない
最後に、強調しておきたいことがあります。
「がんになれば認知症にならない」
「認知症ならがんの心配は少ない」
これは決して安心材料ではありません。
両者は、
人間の細胞が持つ“生と死の制御システム”が、どちらに傾いたかの違い
に過ぎないからです。
どちらも、加齢とともに起こりうる「生物学的な歪み」です。
6.医療の未来へ
がんとアルツハイマー型認知症の関係を解き明かすことは、
- 認知症予防
- がん治療の副作用軽減
- 老化そのものの理解
につながる可能性があります。
外来で感じる小さな違和感は、しばしば医学の本質に通じています。
「なぜ、あの患者さんはがんにならなかったのか」
その問いは、これからの医療を変えるヒントになるのかもしれません。
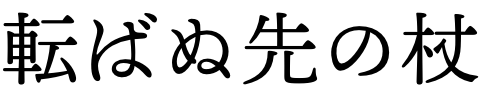


 認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。
認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。