- 現役時代に頑張って働いてきたのに、退職後も節約に励み、我慢を重ねなければならないとしたら、それはとても残念なこと です。
- 重要なポイントとしては、①退職後も適切に資産運用を続けること ②退職後、資産から適切に「 お金を引き出す方法」を知って実践すること ③年金の適切な受給方法を選択すること
- 私がおすすめする「資産運用のやめ方」は、すべての金融資産を一度に売却するのではなく、必要に応じて少しずつ売却し、現金化していく方法です。
- 現役時代に少しずつ積立投資をして資産を作る「資産形成」が大切だといわれていますが、 実は退職後はこの「少しずつ売却して使っていく」という「資産活用」が大切 なのです。
- 「高い山=大きな資産を作ること」を目指すのは大切ですが、「 いかに緩やかな下山ルートを選ぶか=どうすればゆっくり資産を減らしていけるか」を考え、実践することも重要なのです。
- 加齢が資産運用の際の意思決定や行動にも大きな影響をもたらすというのは自然なことであり、皆さんも、「いずれ自分も歳を重ねれば、適切な判断や行動がしにくくなるかもしれない」と考えておいたほうがいいでしょう。
- 私が考える3つの原則を紹介します。 原則の1つ目は、「 退職後の資産は使うためにある」と理解し、資産が減るのを受け入れることです。原則の2つ目は、資産が減ることを許容しつつ、 大きく減らさないようにコントロールする ことです原則の3つ目は、 資産運用を継続する ことです。現役時代に資産運用をやってきた方の中には、退職を機に運用をやめてしまう人もいますが、皆さんはぜひ続けてください。
- 50兆円の相続マーケットでは、毎年 80 ~ 90 代の高齢者から 60 代の高齢者へと資産が引き継がれているのです。 資産を相続した 60 代の高齢者が、その資産を「退職後のため」として抱え込んでしまうとすれば、これは大変もったいない状況だと思います。
- 私は「最初から100歳をゴールに計画を立てる」ことをおすすめ しています。 もし、それよりも早く人生を終えることになれば、余った資産は家族に残したり寄付をしたりすればいいでしょう。足りなくなるよりは、ずっといいのではないかと思います。
- 退職してから 80 歳までの期間を「退職後の生活の前半戦」とし、現役時代からの資産運用を継続しながら一部を取り崩していく、「使いながら運用する時代」とすることをおすすめします。 80 歳から100歳までの 20 年間は、「退職後の生活の後半戦」になります。 それまで運用してきた資産をすべて売却し、残りの 20 年間は預金を取り崩しながら生活する「使うだけの時代」 です。
- まずは「公的年金の受給額に、どれくらい上乗せした生活を送りたいか」を考えてみる のがいいでしょう。
- 退職後の等式は、「生活費=勤労収入+年金収入+資産からの引き出し」
- 働いて得る収入と年金収入で生活費がまかなえる間は、資産を引き出す必要はありません。
- 80 代前半になると認知症の人は全体の 20%程度になると指摘しています。認知症予備軍(軽度認知症)は 20%前後、まったく発症していない人は 60%くらいとのことです。
- 80 歳時点で「保有している金融資産のうち、株式や投資信託で運用している分の売却はほとんど終わっていて、残りの金融資産はほぼ預貯金のみ」という状態になっていれば、金融市場の波乱を心配する必要はないわけです。
- 家族信託の根本的な問題として、 受託者である家族、たとえば子どもたちが、本人に代わって資産運用を継続できるのかという点には課題が残る
- 現実的な対策としては、保有資産を「使い切る資産」と「残す資産」に分け、前者は株式・投資信託を中心に、後者は預金と不動産を中心にして家族信託にするといった振り分けをするのが一つの方法
- 保険というのはリスクに備えるものであり、厚生年金や国民年金が何のリスクに備えるためのものかといえば、「長生きリスク」なのです。
- 長生きしても終身で受け取れる」ことこそが最も重要な特徴のはずです。
- 年金受給を5年繰り下げると、100歳までの必要資産額は3分の2に
- 私がおすすめするのは「 80 歳を目安に運用している資産をすべて売却し、『使いながら運用する時代』を終えて『使うだけの時代』に入る」ことです。退職時点で運用資産をすべて売却する必要はありません。
- 「定率引き出し」は、計画通りの資産残高になりやすい
- もっと簡便に、引き出し率を「 65 ~ 69 歳は3・5%」「 70 ~ 74 歳は4・0%」「 75 ~ 79 歳は4・5%」というように決めておいてもいいでしょう。 大切なことは、引き出し率の設定をそのつど、 恣意的に変えるのではなく、あらかじめルールを決めておくこと です
- 60 代にとっては、金融リテラシーを上げることより、自信過剰にならないようにすることのほうが大切
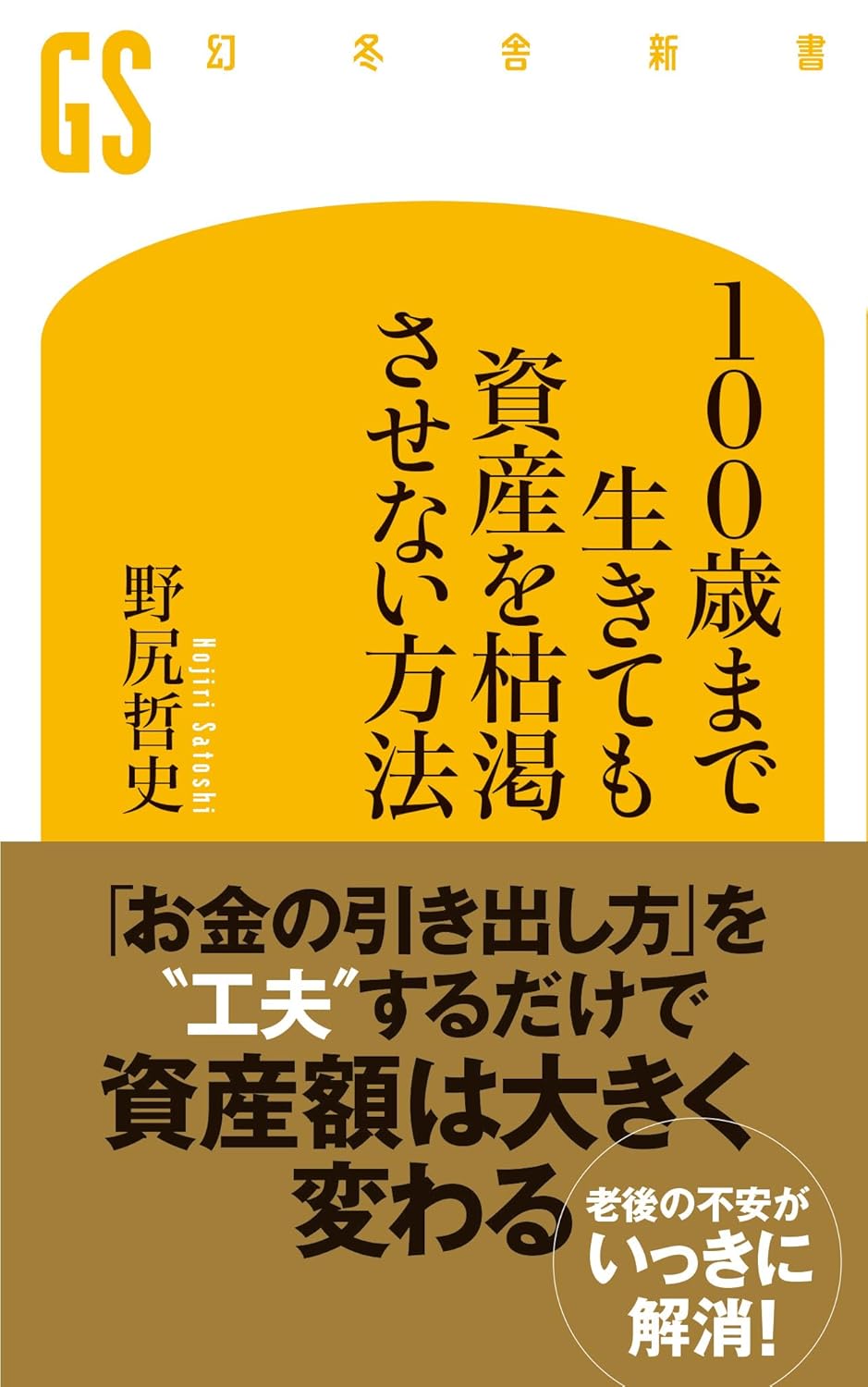
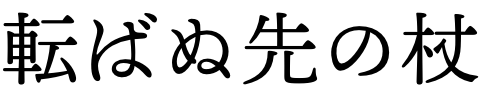
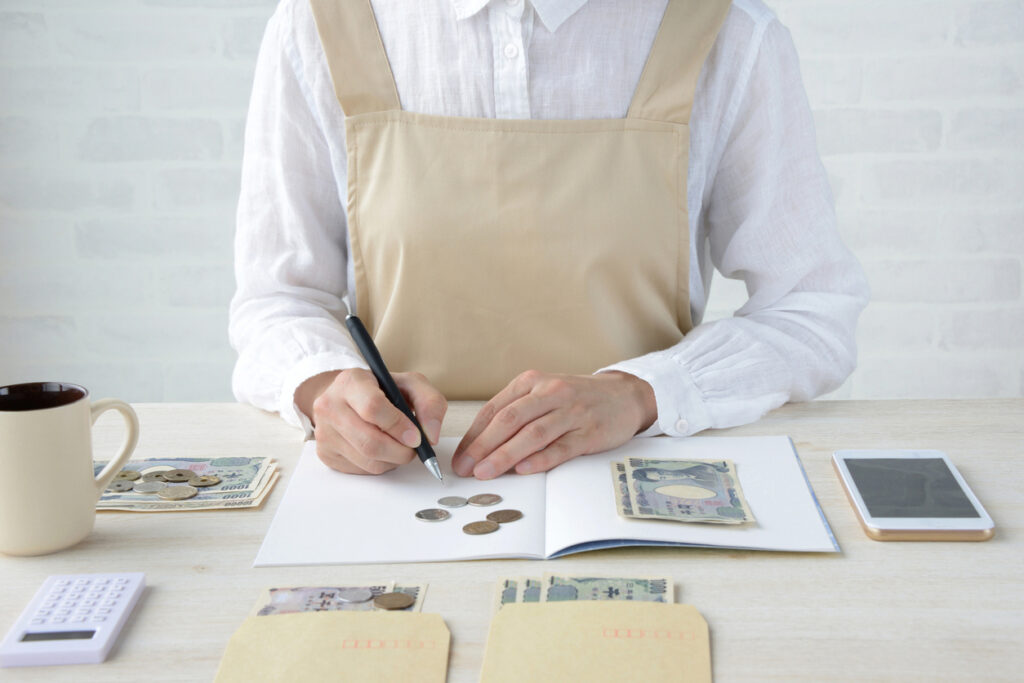

 認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。
認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。