以前は、「なぜ彼らは、こんなにもだらしないのか?」と感じていた著者。しかし、自身が脳梗塞を発症し、後遺症として「高次脳機能障害」という認知機能の障害が残ったことで、かつて取材で「なぜ」と疑問を抱き続けていた人々と、まさに同じ状況に陥ることになります。その体験を通じて綴られた本書は、深い共感と説得力に満ちた内容となっています。
- 自戒も込めて、改めて、提言したい。 貧困とは「不自由な脳」(脳の認知機能や情報処理機能の低下)で生きる結果として、高確率で陥る二次症状、もしくは症候群とでも言えるようなものなのだ。
- 脳の不調を起因とする貧困リスクは、かつて貧困再生産の土壌として僕自身も描写してきた「世代間を連鎖する貧困」とは全くステージの違う、家族資源や教育資源に不備なく育ってきた者にも、キャリア形成後のホワイトカラー層にだって、ある日容赦なく襲い来るものだ。
- 彼らの生き様を綿密に綴った一方で、敢えて著作に書いてこなかった、いくつもの「なぜ?」があった。 なぜ彼らは、こんなにもだらしないのか。
- 周辺者においても、どれほどだらしなくやる気なく見える当事者であっても、その水面下の足搔きを見て取り、責めることなく不自由の緩和を手助けしてやってほしい。
- 問題は、「脳が不自由」という状況が、残念ながら、パッと見て働「けない」ようには見えないことだ。
- 聞き慣れたローン商品である「フラット 35」ですら、100人に3人の割合で債務不履行になると統計されている
- 最大の共通点は、うつ病などの診断で精神科通院中の者が多いことですよね。あと住宅ローン以外にも消費者金融とかに生活費の借り入れがあって、自身の借り入れや支払い状況を自分で把握できていないことがほとんどです。
- 混乱状態にあって自分の状況ややるべきタスクの優先順位を見失っていること。ペットの多頭飼いが多いこと。
- あとは仕事の継続や求職活動に精いっぱいで自宅のメンテナンスに手が回らなくって、物件がいわゆるゴミ屋敷・汚 部屋 化しているケース。
- この「約束の時間を守らないこと」「時間にいい加減なこと」こそは、貧困当事者の取材活動の中で感じ続けていた彼らの大きな共通点だった。
- 同じ約束を守れないの中でも、約束の「すっぽかし」や「ダブルブッキング」が頻発した背景は何か? その背景にあったのは、注意機能ではなく、ワーキングメモリ(短期記憶)の機能低下だった。
- 人が思考や判断をする際に一時的に脳に情報を書き留める脳内のメモ帳のようなものが「書いた途端に消えてしまう」ような症状だ。
- 判断ができない=自己決定ができない
- 彼らはなぜ、自らの危機的状況に対して非常に無自覚でだらしなく、本当に「いざのいざ」というところまで追い込まれてもなお、自ら状況打開に動こうとしないのか? という疑問だ。
- 貧困当事者への取材を通して、行政等の申請書類への記入や、記入のための説明文の読解が困難というのは、極めて共通した証言
- 貧困リスクにまつわる諸々の状況が軒並み悪化しているように思われる現代において、唯一生活保護を取り巻く状況だけは改善に向かって前進しているから。そしてその現在進行形のリアルを実感させてくれるのが、若い現役利用者たちの生声だからだ。
- いまや福祉事務所が最も恐れているのは、申請者の門前払いとかパワハラ対応といった不当な水際作戦をして、それがメディアに取り上げられることだという、空気感。
- 「生活保護の申請に行きづらい雰囲気を変えるとか、行くかどうか悩んでいる人の背中を押してあげるようなアクションは、本来行政がすべきことだと思うんです。テレビCMで流してもいいレベル」
- 彼らは「救うべき存在にもかかわらず、決して救いたくなるような可愛らしい人物像ではないことが多い
- 彼らの問題行動は、本人のパーソナリティに根ざすものというだけではなく、人の脳にはどう足搔いても「そうなってしまう症状」があるからだということ。
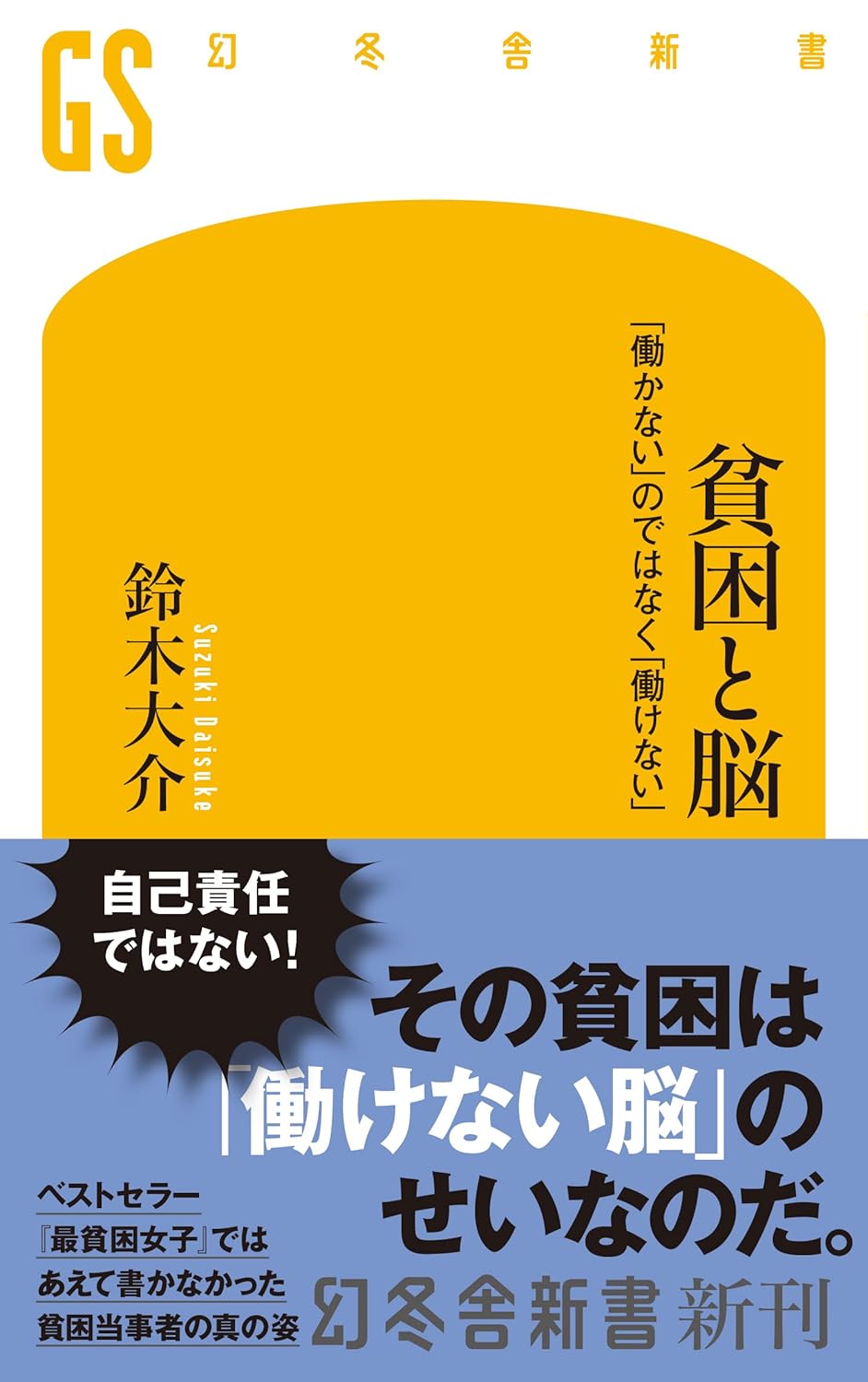
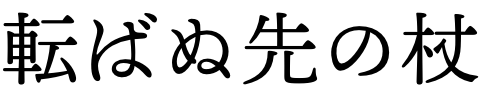


 認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。
認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。