「アニサキスアレルギー」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。最近、知人がこのアレルギーによって日常生活に大きな制約を受けていることを知り、改めてその深刻さに気づかされました。
正直なところ、私自身もつい最近まで「内視鏡で取り除けば終わるのでは?」という程度の認識しかなく、いわゆる食中毒である「アニサキス症」との違いすら理解していませんでした。
しかし近年、このアニサキスアレルギーによって厳しい食事制限を余儀なくされる方が増えています。にもかかわらず、その認知度はまだ低く、私と同じように魚アレルギーやアニサキス症と混同されているケースが少なくありません。
アニサキスアレルギーは、食中毒とはまったく異なるメカニズムで起こる「即時型アレルギー反応」です。魚の中にアニサキスが生きていなくても、アレルゲンとしての成分が残っていれば、症状が誘発される可能性があります。したがって、このアレルギーを正しく理解し、社会全体での認知を広げていくことが求められているのです。
目次
1.アニサキスアレルギーはアニサキス症とは違う!
まず知っておきたいのは、アニサキスとは何かということです。アニサキスとは、主にサバ、イワシ、アジ、サンマ、サケ、イカなどの海産魚介類に寄生する線虫で、人がこれを生や加熱不十分な状態で摂取すると、胃壁や腸壁に侵入し、激しい腹痛や嘔吐、下痢などを引き起こすことがあります。これがいわゆる「アニサキス症」で、急性の食中毒の一種です。内視鏡などで虫体を取り除けば症状は治まりますし、虫体が死ねば自然に軽快します。
2.アニサキスアレルギーとは即時型アレルギー
一方で、アニサキスアレルギーは、この虫体に含まれる特定のタンパク質(主に分泌排泄物や死んだ虫体由来の抗原)に対して、免疫系が過剰に反応してしまうことによって引き起こされます。こちらは胃や腸の機械的な刺激ではなく、免疫反応によるアレルギー症状が主です。症状は、蕁麻疹、呼吸困難、腹痛、嘔吐、さらにはアナフィラキシーショックに至ることもあり、非常に危険です。
3.アニサキスアレルギーが厄介な理由
厄介なのは、アニサキスアレルギーは加熱や冷凍をしてもアレルゲンが完全に無害化されないという点です。アニサキス症(寄生虫としてのアニサキスが生きていることで発症する食中毒)は、加熱や冷凍処理によって防ぐことができます。しかし、アレルギーは死んだアニサキスが魚の中に残っていたとしても、それに反応してしまうため、防ぐことが極めて難しいのです。焼き魚や煮魚を食べたにもかかわらず、原因不明のアレルギー症状を起こしたという人の中には、実はアニサキスアレルギーであるケースが隠れている可能性があります。
4.アニサキスアレルギーは広範な食事制限
アニサキスアレルギーの患者さんは、非常に広範囲な魚介類の摂取を制限しなければならなくなります。魚そのものだけでなく、アニサキスが寄生していた可能性のある魚の加工品、出汁、調味料、さらには飲食店での調理器具や油の使い回しなど、日常のあらゆる場面に注意を払う必要があります。例えば、「煮魚の煮汁がほんの少しかかっただけでも症状が出た」という報告もあるほどです。
5.アニサキスアレルギーの診断が難しい
実際にアニサキスアレルギーと診断されるまでには、長い時間がかかることが少なくありません。「魚を食べると具合が悪くなる」ということで、単に魚アレルギーとされることが多く、その原因がアニサキスであることに気づかれないまま過ごしている人もいます。しかし、魚そのものにアレルギーがあるわけではないため、アニサキスが寄生していない魚であれば問題なく食べられるケースもあります。逆に、アニサキスに寄生されやすい魚を避けていたにもかかわらず、アレルゲンが残っていたことで症状が出てしまうこともあり、自己判断は非常に難しいのです。
アニサキスアレルギーは、血液検査でアレルゲン特異的IgE抗体を調べることで診断されることが多いですが、検出できないこともあり、確定診断には専門の医師のもとでの詳細な問診と検査が不可欠です。また、発症後はエピペン(アドレナリン自己注射薬)の携帯を勧められることもあります。
6.まとめ
魚食文化が根強い日本において、魚介類の摂取を避けることは生活の質を大きく左右します。外食はもちろん、家庭での調理においても配慮が必要で、周囲の理解と協力も不可欠です。アニサキスアレルギーの認知が進むことで、患者さんが不必要な不安や誤解に悩まされることなく、安心して生活を送れる社会が求められています。
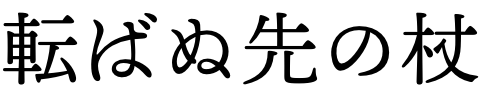


 認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。
認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。