誰もが、自宅・職場・公共施設などで建築とは関わらずを得ません。しかし、系統だてて学ぶ機会は少ないものです。この本は、まさに1冊でおおよそ『建築の教養』を学ぶことができます。お薦めです。
- 「建築」とは何かを一言で表しましょう。 「建築」とは「強・用・美」 である。
- 非常に単純化して言えば、「建築は重力や地震で壊れてはいけないし(強)、使いやすくて快適でないといけない(用)。また、見た目に格好よくないといけない(美)。そして、このうちどれかが欠けてもいけない」ということです。
- 1995年の兵庫県南部地震以降、最大震度である震度7を記録した地震は現在までにすでに7回発生しています(1995年 兵庫県南部地震、2004年 新潟県中越地震、2011年 東北地方太平洋沖地震、2016年 熊本地震前震および本震、2018年 北海道 胆振 東部地震、2024年 能登半島地震)。
- 日本の建築基準法に定められた耐震基準では、 震度5強程度の地震に対して損傷しない よう設計が行われます。上から2番目の震度6強ではない、そのさらに二つ下のランクである震度5強なのです。
- 震度5強で損傷しないようにしているということは、震度6弱で損傷するかもしれないということです。震度6強や震度7の大地震であれば損傷する可能性は非常に高いでしょう。 大地震に対しては、 建物が損傷するのは大前提 なのです。 耐震とは言うものの、なんとも期待外れな性能です。
- 震度5強の揺れによって建物にかかる地震の力と震度7の揺れによって建物にかかる地震の力は、なんと5倍も違います。
- 大地震に対しても損傷しない建物をつくろうと思うと、建物の耐震性を5倍に高めないといけないのです。
- もし木造で自宅を建てようと考えているのであれば、標準よりも壁の量が5倍なくてはなりません。 広いリビングはつくれず、大きな窓も取れない、なんとも魅力のない家になってしまうことでしょう。
- 「損傷」の意味をしっかりと理解することが重要です。建物が「損傷」することと、建物が「倒壊」することの間には大きな隔たりがあります。
- 損傷というのは、壁を留め付けている釘が少し緩んだり、壁が一部ポロポロと落ちるような状況を想定しています。
- 鉄筋コンクリートは、圧縮には強いが引張には弱いコンクリートと、引張には強いが圧縮には弱い鉄筋が、相互に弱点を補いあうことで優れた性能を発揮します。
- 鉄筋を入れないといけない≒ひびが入っても仕方がない
- ひび割れの本数や幅を許容値内に納まるように制御することが重要です。 ひび割れとは上手に付き合うしかありません。
- 法律上の想定では、震度7は2回来ない のです。大地震で建物が損傷しても、倒壊さえしなければ人命を守ることができます。
- どれくらい耐震性を高めればいいのかですが、日本建築学会の元会長である 竹 脇 出 らがすでに検討を行っています。
- 大地震に一度は耐えることができるとされる現行の耐震基準の1・5倍というのがその答えです。もちろんどんな地震が起こるかわからない以上、現行の耐震基準の1・5倍で建物をつくれば絶対に安全というわけではありません。
- そもそも建築基準法の第一章の第一条、まさに最初の一文に〝この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて〟と記載されています。法律自身が「最低限のことしか規定していませんよ」と宣言しているのです。
- 鉄より強くて、硬くて、加工しやすくて、そして地球上に大量にある、そんなものは存在しません。
- 「強」にあたる建物の安全性に 責 を負う建築士を「構造設計者」、「用」にあたる建物の機能性に責を負う建築士を「設備設計者」、そして最後の「美」にあたる建物のデザインに責を負う建築士を「意匠設計者」と呼びます。
- 建築士がしっかりと指示しない限りは、真に地震に強い建物にはならないのです。建築士が構造のことを知らない弊害は大きいと言えます。
- 個人が住宅を建てるにあたっては、目の前で打ち合わせしている建築士は「美」の専門家であって「強」の専門家ではない
- 一般的な住宅よりも耐震性を高めたいなら、「○○構造設計事務所」という看板を掲げている建築士に相談してください。
- 1971年の改正は1968年の十勝沖地震、1981年の改正は1978年の宮城県沖地震、そして2000年の改正は1995年の兵庫県南部地震を受けての結果です。 大きな地震のたびに基準がアップデート されていることがわかります。
- 2000年以降は基準が改正されていません。改正から2024年までに震度7を記録した地震が6回も起こっていることを考えると、現在の基準は概ね及第点という認識なのでしょう。
- 特に1981年の改正は大きな節目であり、この基準に適合している建物は「新耐震」の建物と呼ばれ、それ以前の基準にしか適合していない「旧耐震」の建物と区別されます。耐震の規定に関する大幅な改正がなされましたが、木造住宅を例にとると、新耐震では旧耐震の約1・5倍の壁や筋かいが設置されることになります。
- 当時最新であった1981年の基準に適合している新耐震の建物は、兵庫県南部地震において、それ以前に建てられた建物に比べて明らかに被害が小さくなっていました。
- 構造の専門家と呼べるのは構造設計一級建築士だけですが、2024年時点で1万人強しかいません
- 伝統構法は過去の地震で大きく被害を受けています。しかし、たまたま伝統構法の建物が被害を受けず、新しい建物が被害を受けた地域があると、やはり伝統構法はすごい、日本の大工はすごい、という説が流れてしまいます。
- 「五重塔は倒れない」という神秘は、神秘のままで置いておきたいような気もしますが、実際にはそんなものはなかったようです。単にいい地盤の上に高い塔を建てたからという理由で、今日までその姿をとどめていると考えられます。
- 地震によって地盤は前後左右、上下に揺れますが、被害のほとんどは前後左右、つまり水平方向の揺れによってもたらされます。
- 鉛直方向は建物を支えるだけの硬さと強さがあり、水平方向は柔らかくてほとんど力を伝えない、というものがあればいいということになります。
- 免震は現時点で最高の地震対策技術 です。そして、これからもそうであり続ける可能性が高いでしょう。それだけ免震は優れています。
- 災害時に負傷者の受け入れ拠点となる地域の総合病院などでは、ほぼ例外なく免震が採用されています。実際、2004年の新潟県中越地震やそれ以降の大地震では、「病院を免震にしておいてよかった」という報道が必ず出てきます。
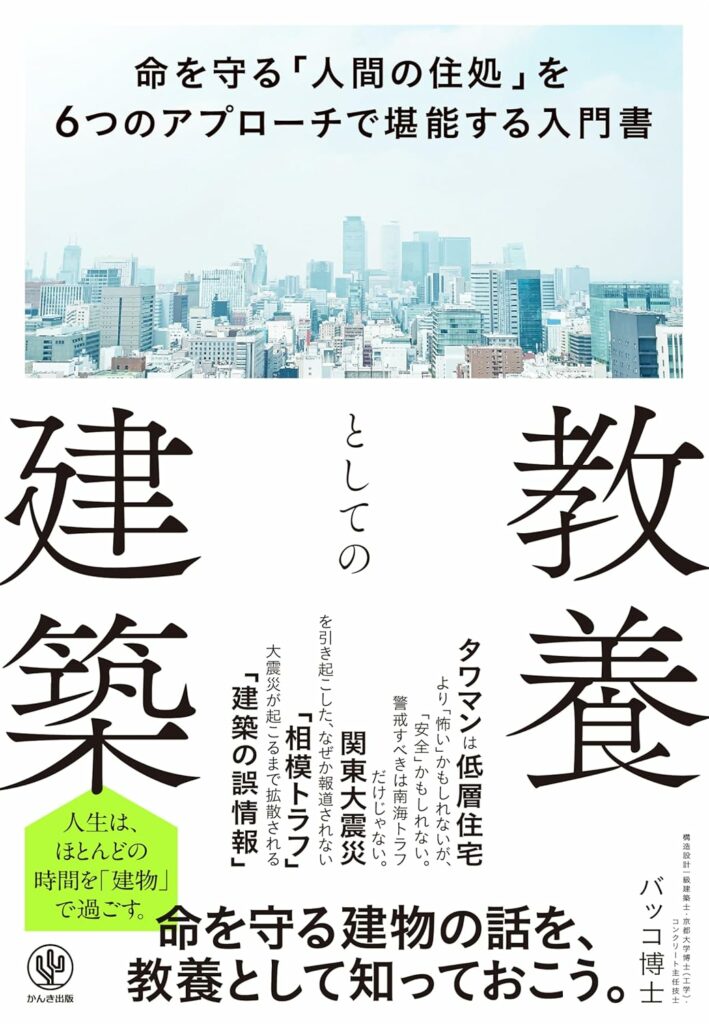
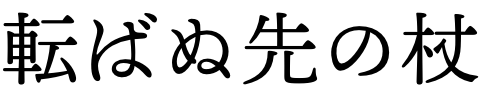


 認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。
認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。