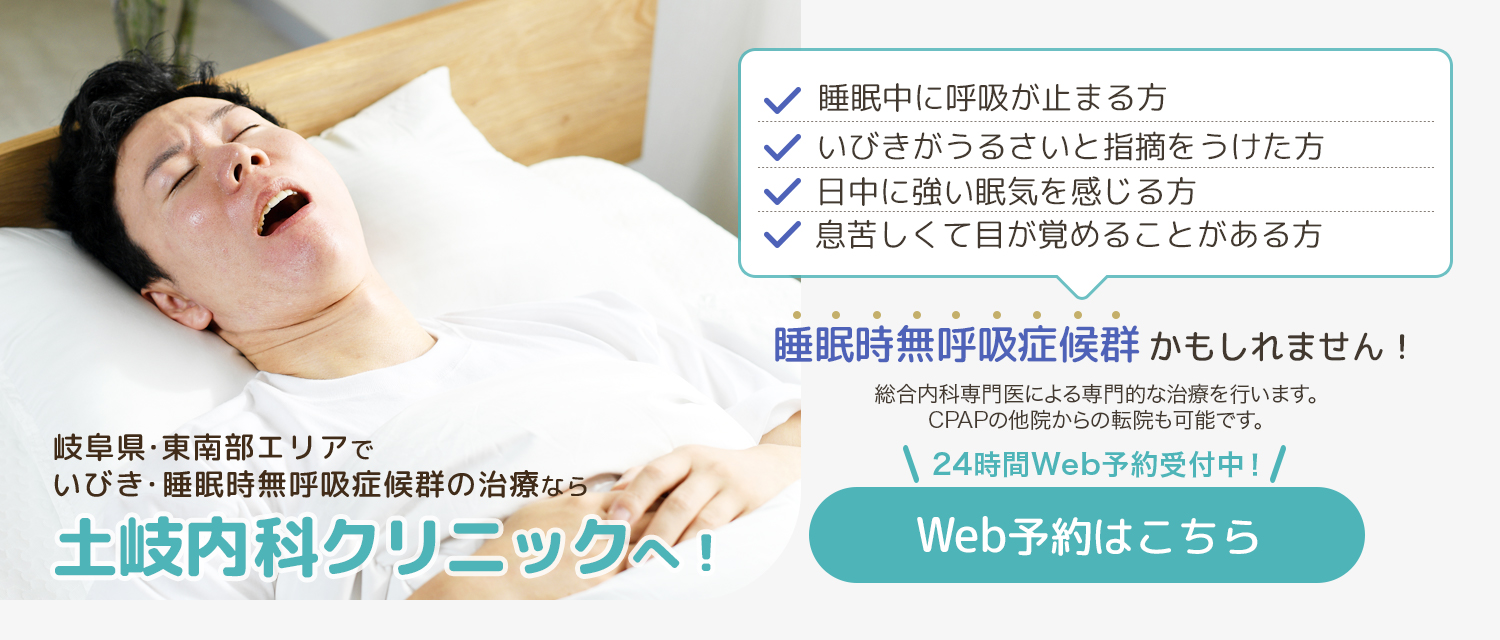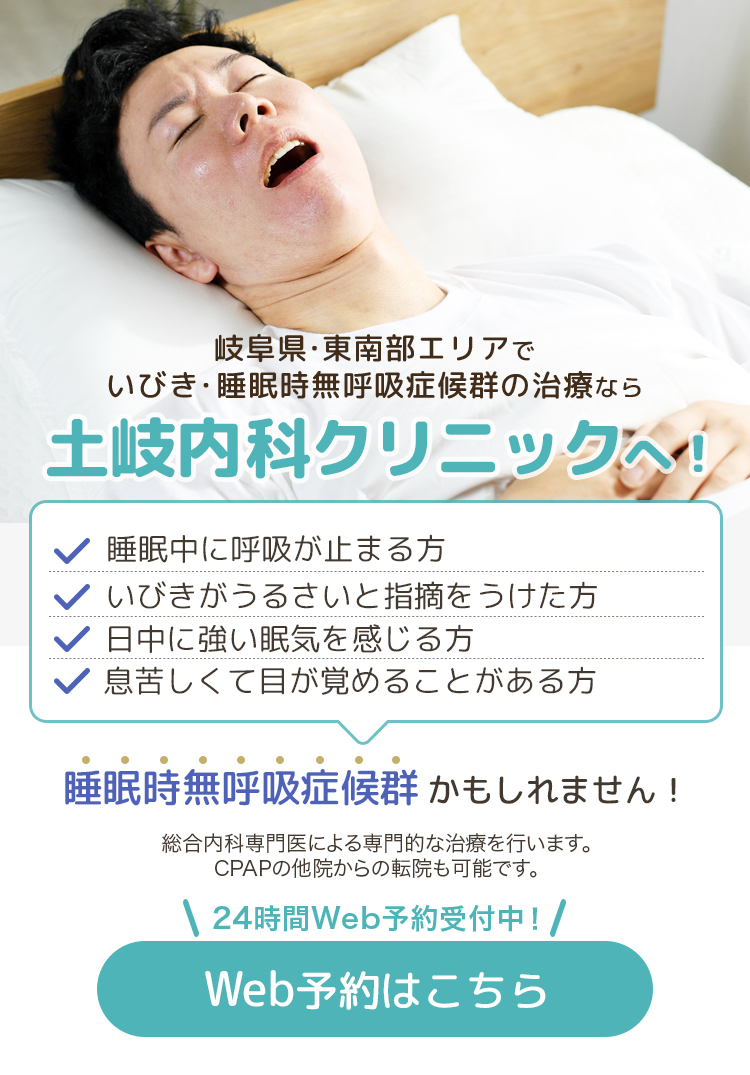睡眠時無呼吸症候群に
なりやすい方
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が止まる病気です。放っておくと、日中の眠気や集中力低下だけでなく、高血圧や心臓病などのリスクも高まります。今回は、SASになりやすい人の特徴や予防法について詳しく解説していきます。
SASは誰にでも起こりうる病気ですが、特に以下のような特徴を持つ人は注意が必要です。
- 肥満
- 肥満はSASの最も大きなリスク要因の一つです。首回りに脂肪がつくと、気道が狭くなり、睡眠中に閉塞しやすくなります。BMI(体格指数:体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)で算出)が25以上の場合は、SASのリスクが高まると言われています。肥満の方は、体重管理を心がけることがSAS予防の第一歩です。具体的な方法としては、1日30分のウォーキングや、食事のカロリーを控えるなどが挙げられます。
- 見た目
- ASになりやすい人の外見的な特徴としては、首が太い、あごが小さい、顔が大きいなどが挙げられます。これらの特徴は、気道が狭くなっている可能性を示唆しています。あごが小さい、首が太いなど、生まれつきの骨格もSASのリスクに影響します。
- 首の太さ
- 首が太い人は、気道が狭くなりがちです。男性で首回り43cm以上、女性で38cm以上ある場合は、SASのリスクが高まるとされています。首回りが太い方は、SASのリスクが高いと言えるでしょう。
- あごの小ささ
- あごが小さいと、舌が気道を塞ぎやすくなるため、SASのリスクが高まります。あごが小さい方は、舌が気道を圧迫しやすいため注意が必要です。
- 性別
- 一般的に、男性は女性よりもSASになりやすいと言われています。これは、男性ホルモンの影響で気道が狭くなりやすいことや、肥満が多いことなどが原因と考えられています。男性は女性に比べてSASの発症率が高い傾向にあります。
- 遺伝
- 家族にSAS患者がいる場合は、遺伝的にSASになりやすい体質である可能性があります。ご家族にSASの方がいる場合は、遺伝的にSASのリスクが高まる可能性があります。
- 加齢
- 加齢とともに、筋肉の衰えや気道のたるみなどが起こり、SASのリスクが高まります。特に、40代以降は注意が必要です。年齢を重ねるごとに、SASのリスクは高まっていきます。
- 鼻づまりなどの鼻症状
- アレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎など、鼻の病気がある人は、鼻呼吸が困難になり、口呼吸になりがちです。口呼吸はSASのリスクを高めるため注意が必要です。鼻づまりがある方は、口呼吸になりやすく、SASのリスクを高めてしまいます。
- アルコール・睡眠薬
- アルコールや睡眠薬は、筋肉を弛緩させる作用があるため、気道を狭くし、SASのリスクを高めます。アルコールや睡眠薬の摂取は、SASのリスクを高める可能性があります。特に、就寝前の飲酒は避けましょう。
- たばこ
- 喫煙は、気道の炎症を引き起こし、SASのリスクを高めます。また、喫煙はSASの症状を悪化させる可能性もあります。喫煙は、気道を傷つけ、SASのリスクを高めるだけでなく、症状を悪化させる可能性もあります。禁煙を心がけましょう。
- アデノイドや扁桃肥大
- アデノイドや扁桃が肥大していると、気道を狭くし、SASのリスクを高めます。特に、子供に多い傾向があります。アデノイドや扁桃肥大は、子供のSASの原因となることがあります。
- 口呼吸
- 口呼吸は、舌が喉の奥に落ち込みやすくなるため、SASのリスクを高めます。口呼吸の習慣がある方は、SASのリスクを高める可能性があります。
- 舌のくせ
- 舌を前に突き出す、歯で噛むなどの癖がある人は、SASのリスクが高まる可能性があります。舌の癖も、SASのリスクに影響を与える可能性があります。
睡眠時無呼吸症候群の予防法
SASの予防には、以下のような方法があります。
生活習慣の改善

- 適正体重の維持
- 1日30分のウォーキングや、間食を控えるなど、具体的な行動を心がけましょう。
- バランスの取れた食事
- 野菜、果物、魚などを積極的に摂取し、栄養バランスに気を配りましょう。
- 適度な運動
- 軽いジョギングや水泳など、無理のない範囲で運動を習慣化しましょう。
- 禁煙
- 禁煙外来の利用や、ニコチンパッチの使用など、禁煙をサポートするサービスを活用しましょう。
- アルコールの摂取量を控える
- 特に、就寝前の飲酒は避け、適量を守って飲酒しましょう。
- 睡眠薬の使用を控える
- 睡眠薬の使用は、医師の指示に従い、必要最低限にしましょう。

睡眠環境の改善

- 横向きで寝る
- 横向きで寝ることで、気道が確保されやすくなります。
- 枕の高さを調整する
- 自分に合った高さの枕を使用することで、気道を圧迫するのを防ぎます。
- 寝室の湿度を適切に保つ
- 乾燥した空気は、気道を刺激し、SASの症状を悪化させる可能性があります。加湿器などを活用し、適切な湿度を保ちましょう。

口呼吸の改善

- 鼻呼吸を意識する
- 日頃から鼻呼吸を意識することで、口呼吸の習慣を改善することができます。
- 口テープを使用する
- 就寝時に口テープを使用することで、口呼吸を防止することができます。

医療機関への相談

- SASの疑いがある場合は、医療機関を受診し、検査を受ける

SASは、適切な予防と治療を行うことで、症状を改善し、合併症のリスクを減らすことができます。
気になる症状がある場合は、岐阜県土岐市にある土岐内科クリニックまでお気軽にご相談、受診ください。