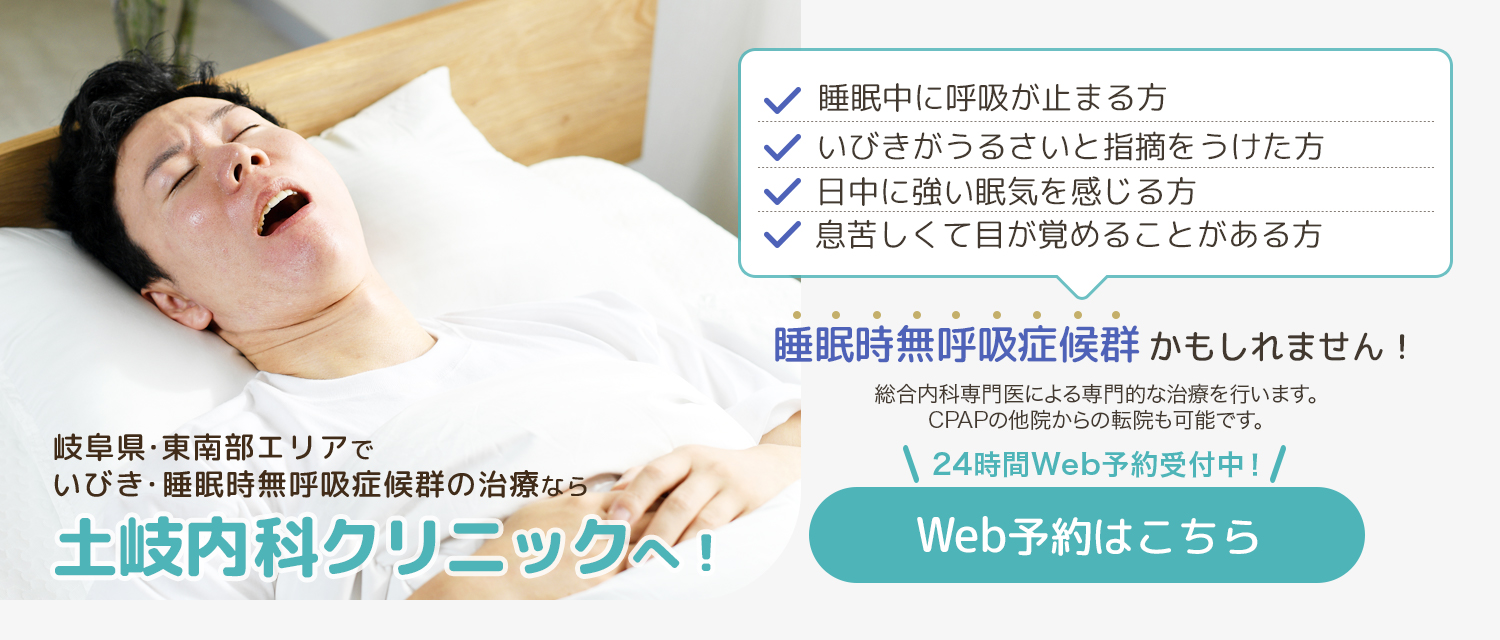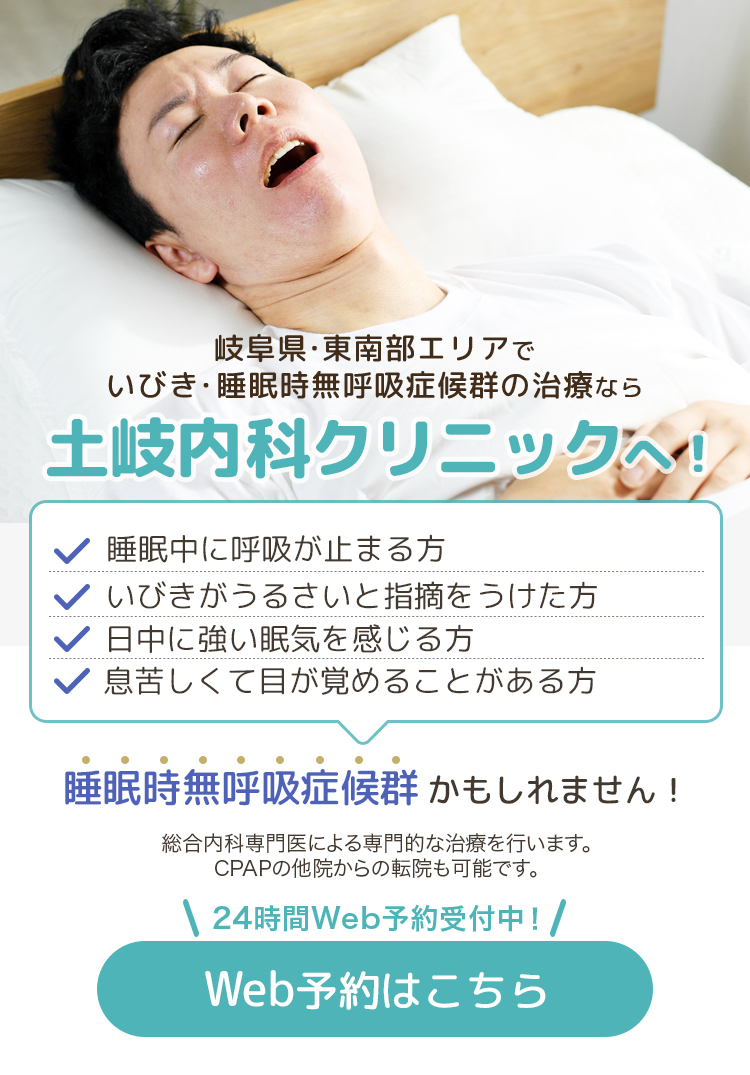寝汗をよくかく・寝苦しい・熟睡できない
「夜中に何度も汗でびっしょりになって目が覚めてしまう…」「朝起きた時に体がだるくて、全然寝た気がしない…」
現代では多くの人が、寝汗や寝苦しさ、熟睡できないといった睡眠の悩みを抱えています。
これらの症状は、日中の集中力やパフォーマンスを低下させるだけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。
また、これらのお悩みは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)との関連も指摘されており、注意が必要です。
この記事では、寝汗、寝苦しさ、熟睡できないといった症状の原因と、その改善策について、睡眠時無呼吸症候群(SAS)との関連性も踏まえながら詳しく解説していきます。
寝汗・寝苦しい・熟睡できない原因は?

寝汗や寝苦しさ、熟睡できないといった睡眠トラブルの原因は、実に様々です。
まず考えられるのは、寝室の環境です。室温や湿度が高すぎたり、寝具が合っていなかったりすると、寝汗をかきやすくなり、寝苦しさを感じてしまいます。
また、体の不調が原因で寝汗をかくこともあります。例えば、風邪をひいて発熱している時や、更年期障害、甲状腺機能亢進症などの疾患が挙げられます。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)も、これらの症状の大きな原因の一つです。SASは、睡眠中に呼吸が止まる病気で、大きないびきや日中の強い眠気などの症状が現れます。
寝汗をかくのは、SASによって呼吸が止まり、血液中の酸素濃度が低下することで、体がストレスを感じ、自律神経が乱れるためと考えられています。
また、SASの人は、睡眠が浅くなりがちで、熟睡できないことが多いのも特徴です。
精神的なストレスも、自律神経のバランスを乱し、寝汗や睡眠障害を引き起こす可能性があります。日々の不安や緊張、過剰なストレスを抱えている方は、注意が必要です。
さらに、生活習慣の乱れも睡眠の質を大きく左右します。寝る直前の食事や飲酒、カフェインの摂取、不規則な生活習慣などは、睡眠の質を低下させる要因となります。

寝汗・寝苦しい・熟睡できない原因に対する改善策は?
寝汗や寝苦しさ、熟睡できないといった症状を改善するためには、原因に応じた対策を講じることが重要です。 SASが疑われる場合は、早めに専門医に相談することをおすすめします。
1.睡眠環境の見直し
- 室温と湿度
- 夏は26~28℃、冬は18~22℃を目安に、エアコンや扇風機などを活用して室温を調整しましょう。湿度は50~60%が理想的です。除湿機や加湿器を活用するのも良いでしょう。
- 寝具
- 通気性・吸湿性に優れた素材の寝具を選びましょう。羽毛布団や羊毛布団、麻のシーツなどがおすすめです。また、枕の高さも重要です。自分に合った高さの枕を選び、首や肩に負担がかからないようにしましょう。
- パジャマ
- 吸水性・通気性の良い綿や麻素材のパジャマを選びましょう。締め付けの少ないゆったりとしたデザインのものもおすすめです。
2. 生活習慣の改善
- 食事
- 寝る3時間前までに食事を済ませましょう。特に、消化に悪い脂っこいものは避け、寝る前に温かい牛乳やハーブティーを飲むのもおすすめです。
- カフェイン・アルコール
- 寝る前のコーヒーや緑茶、アルコールは控えましょう。
- 睡眠時間
- 毎日同じ時間に寝起きし、7時間程度の睡眠時間を確保しましょう。
- リラックスタイム
- 寝る前にリラックスできる時間を取りましょう。読書や音楽鑑賞、ストレッチなどがおすすめです。ぬるめのお風呂に浸かるのも効果的です。
- 運動
- 適度な運動を習慣化しましょう。ただし、寝る直前の激しい運動は避けましょう。
- 体重管理
- 肥満はSASのリスクを高めるため、適正体重を維持しましょう。
3. 医療機関への相談
上記の対策を試しても改善が見られない場合や、他に気になる症状がある場合は、医療機関を受診しましょう。
特に、大きないびき、日中の強い眠気、起床時の頭痛、夜間の中途覚醒、頻繁な寝汗など、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる症状がある場合は、早めに専門医に相談することが大切です。
SASの検査では、睡眠中の呼吸状態や血液中の酸素濃度などを測定します。 治療法としては、CPAP療法(経鼻的持続陽圧呼吸療法)などがあります。
当院では睡眠時無呼吸症候群の検査、診断、治療を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
これらの症状に心当たりがある方は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。早めに医療機関を受診し、検査を受けることをおすすめします。