通常の内科診療所ではあまりないことですが、当院は、毎月裁判所や弁護士さんから電話がかかってきます。これは、当院が認知症を専門としているからです。これらの大部分は、遺言作成に関するものなのです。
最近は、遺言を残される方が増えてきています。しかし、遺族のためにと思って書いた遺言がかえって、「争族」の原因となっているのです。遺言内容に不満を持つ遺族が、弁護士や裁判所を通じて、遺言を書いた時点での認知機能について問い合わせてくるのです。
今回の記事では、月に1,000人の認知症患者さんを診察する専門医の長谷川が、争族の種にならないための注意点をご紹介します。
目次
1.認知症になったら遺言は書けない?
そもそも、認知症になったら遺言は書けないのでしょうか? 民法では、「遺言者は、遺言をするときにおいてその能力を有しなければならない」(民法963条)と定義されていますが、「その能力」の明確な基準は実はありません。
1-1.MMSE20点以上であれば可能なことが多い
一般的には、MMSE(Mini Mental State Examination:ミニメンタルステート検査)で30点満点で20点以上であれば、物忘れはあっても日常生活は自立していますので、遺言作成は可能と考えます。しかし、過去の判例では、遺言内容があまりに複雑な場合は、無効と判断されたこともあります。
1-2.MMSE20点未満は困難なことが多い
通常、MMSEが30点満点で20点を切ってくると生活の中でも援助が必要になります。そのため、一般的には、契約能力や遺言作成能力はないと判断します。しかし、1-1とは逆に、遺言内容が極めてシンプルな場合は、有効と判断されたこともあるのです。
1-3.健康なうちに作成を
つまり、遺言作成と認知症のレベルについて明確な基準はないのです。そのため、周囲からも認知症を疑われることもなく、生活が自立している段階で、遺言作成をすることが大事になります。

2.問い合わせ内容は
当院に、問い合わせされるケースは以下のようなものです。
2-1.遺言作成能力は?
患者さんが遺言を作成した時期に、当院に通院されていたケースです。遺族、遺族の弁護士、裁判所のいずれから、作成当時の認知症の程度について、遺言を作成する能力があったか否かの問い合わせが来るのです。
2-2.死後8年目の事もある
問いあわせは亡くなって、数か月程度経ってからのことが多いのですが、中には、8年前のこともありました。相続も終わり、土地の登記も終わったと思われた段階での問い合わせもあるのです。
2-3.専門外の医師の診断書もフル出演
問合せは、当院だけでないこともあります。風邪で通院した診療所、水虫でかかった皮膚科、白内障でかかった眼科など、受診したすべての医療機関での診断書を集めている方もいます。もちろん、どの診療所も、通院した事実以上の記載はされないので、まったく意味はないのですが・・・。
3.トラブル内容の例
実際のトラブルは以下のようなものです。
3-1.状態悪化時の遺言作成
我々も驚くような時に遺言作成がされていたことがあります。患者さんが、1週間前から食事もとれず、水分だけ。あと数日で亡くなると思われていた時期に遺言を作成されていたのです。患者さんはその1週間後に死去。亡くなる1週間前の遺言が有効とは思えません。
3-2.一部の相続人が誘導?
さすがに遺言内容までは医療従事者には分かりませんが、訴訟をおこした遺族や弁護士によると、相当に偏った内容の遺言書の様です。内容からして、一部の相続人が誘導して書かせたと思われても止むを得ないのです。
3-3.立会人2名とはいえ信用できないケースも
公正証書遺言を作成する場合、成年2人に立会人(証人)として同行もしくはベッドサイドに来てもらう必要があります。しかし、立会人には、未成年者や相続人等以外であれば誰でもなれます。
信託銀行の行員2名が立ち会う場合もあります。つまり、遺言を作成することで利益が得られる可能性のある人たちが立ち会っているのです。とても、彼らが「遺言者に遺言作成能力があるか否か」を正確に判断することは期待できないのです。

4.裁判になったらどうなる?
裁判所からの電話の場合は、すでに裁判になっていることが大半です。私自身、遺言無効裁判の鑑定人をしたことがありますが、「あまり関わりなくない」が本音です。
*鑑定人:訴訟などで、一定分野の専門的知見に基づき意見を述べる人。訴訟法上の鑑定人。
4-1.家族関係は崩壊
裁判になれば、家族関係は崩壊します。裁判では、弁護士・鑑定する医師などにより双方で相手の遺言作成時の状態などを想像して、有効・無効を主張しあいます。一度でもそんなことをしてしまえば、二度と家族関係の修復は不可能です。
4-2.白黒はつかない
私の経験では、食事が全くとれない状態で点滴だけで1か月経ち、前日の夜には不穏で安定剤を注射をされている患者さんが遺言作成することは不可能と主張したケースがありました。しかし、そんな状態でも、遺言作成は可能と主張する医師もいるのです。
そのため、家族は、自分の思い通りの意見を証明してくれる医師を探します。そんな家族は相談時は、にこやかですが、意見が合わないとなると怒ってしまいます。まさに、「笑って来院、怒って転院」です。このような理由から、「出来たら関わりたくない」のです。
4-3.弁護士が儲かるだけ
医師でも意見が分かれると、裁判所でも白黒をつけることは不可能です。白黒がつかないと、裁判所は、双方の弁護士を呼んで、適当なところで落としどころを探します。結果、白とも黒ともいえない条件で、双方に納得してもらって終わりです。つまり、遺言に関係した裁判では、結局弁護士が儲かるだけで、家族関係が崩壊した相続人には何のメリットもないのです。
5.対策
ならば、どんな対策が必要でしょうか?
5-1.遺言作成時に医師の診断書
認知症と疑われた場合の、判例には有効、無効それぞれの判例がありました。しかし、認知症ではない方であれば、遺言は有効になります。そのため、必須ではありませんが、認知症専門医の診察を受けて、「認知症ではない」という診断書をもらってからの遺言作成は相当に信憑性が高まると思われます。
5-2.そもそも、偏った遺言書は無効
そもそも偏った内容の遺言書は無効になります。最低でも遺留分は侵害しない内容にしましょう。その点、信託銀行を利用する場合は、遺留分を侵害した遺言書は受け付けてくれないので安心です。
5-3.たくさんある人は、毎年の贈与を
これは資産が多い人が対象です。相続税の軽減には、贈与が有効です。これは知り合いの方がおこなっている方法です。毎年、自分の誕生日に子供や孫といった相続人を集めます。そして参加者それぞれに100万円を渡すというものです。その際、欠席者には渡さないというルールを作っておけば、皆さん必ず出席します。
5-4.付言を有効利用
遺言書には、遺言の最後に「付言」を書くことが出来ます。付言では、遺言を書くに至った理由、相続人への感謝の気持ち、意志を伝えることが出来ます。
相続とは、完全な平等は不可能です。仮に100万円の遺産を3人の子供で割っても割り切れません。そんな不平等を埋めるのが付言です。「遺産の分割には多少の不平等はあったが、愛情は平等です」とでも書かれていれば、無用な争いが減るかもしれないのです。
6.まとめ
- せっかく書いた遺言が、争いの種になることがあります。
- 家族関係を崩壊させる裁判は、避けたいものです。
- そのためにも、医師の診断書をつけて、遺留分を侵害しない、付言で思いを伝えるような遺言を残したいものです。
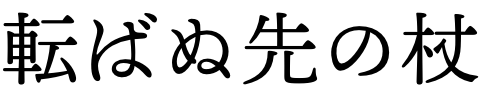


 認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。
認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。